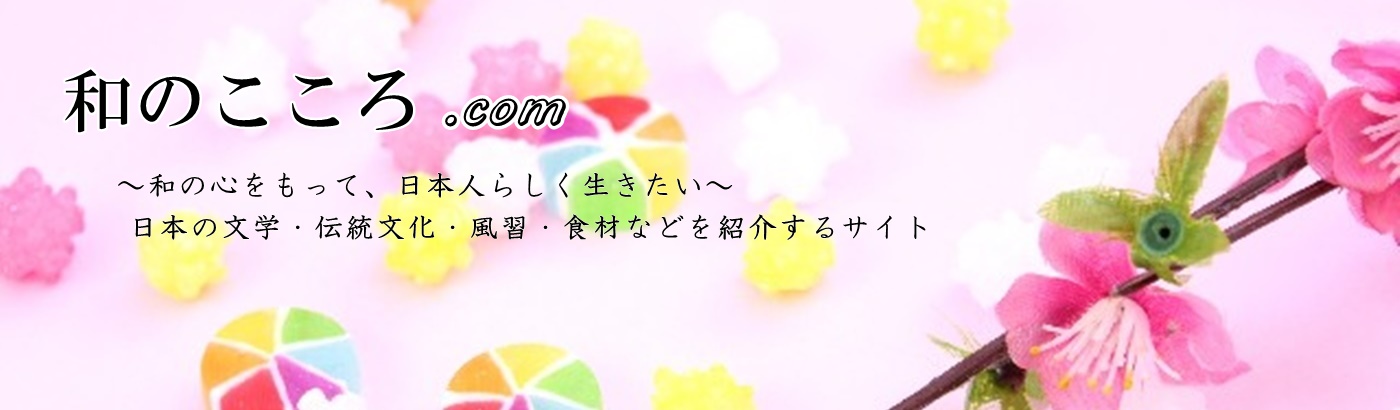この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です。

こんにちは。
大正時代は、たった15年しかありません。しかし大正デモクラシー、大正ロマンなどの言葉が残るように、人々の考え方が大きく変化した、思想の過度期でした。
その大正時代の文豪として知られるのが、今回ご紹介する芥川龍之介です。芥川龍之介といえば、夏目漱石の門下生で、太宰治や坂口安吾など、多くの後輩に影響を与えたことで知られます。
彼の作品の特徴として、古典のパクリが多いという指摘があります。
そういわれると身もフタもないのですが、彼は「換骨奪胎(かんこつだったい)」という手法が得意だったのです。
「換骨奪胎」は、辞書っぽく説明すると、古人の詩文の表現や発想などをもとにしてそれに創意を加え、自分独自の作品として価値あるものにすることです。
この『羅生門』の場合、12世紀に成立した説話集・『今昔物語集』の2つのお話をモチーフに芥川流の創意工夫を加え、新しい作品に仕上げたということですよ。
人間の本質,エゴというものをかなり冷めた目で見つめた作品なので、これがデビュー作ともいえるもの(23歳のときの作品)だと知った当時、「暗っ!でも、さすがだなぁ」と思いました。
私は結構、そんな芥川作品が好きです! 短い作品がほとんどなので、興味を持たれたら是非読んでみてください♪
今昔物語集との違い

『羅生門』の典拠(てんきょ)は、『今昔物語集』29巻「羅城門(らじょうもん)」と、31巻「売魚」(一部引用)の2つです。
羅城門はとっくの昔に失われていますが、平安時代、京の都の南端に実際にあった巨大な建造物です。800年頃に建てられ、980年の台風で倒壊した頃には、すでに荒廃していたようです。
都の貴族たちは、この門から南を、魑魅魍魎のいる恐ろしい世界・異界ととらえていました。この門が、この世界と異界の境界だったのです。
この羅城門は、室町時代頃から「羅生門」という字で表されるようになりました。ですから、今昔物語集の「羅城門」を芥川が「羅生門」と変えたのに、特別な理由があったのかどうかはよくわかりません。
登場人物と簡単なあらすじ

★ 登場人物
登場人物は2人です。
●下人(げにん)
仕事を失った若者。生きるために盗人になるしかないと思い悩んでいる
●老婆
羅生門に打ち捨てられた死んだ女の髪の毛を抜いて、かつらを作って売ろうとしていた
★ 簡単なあらすじ
仕事をクビになった下人が、これから生きるためには盗人になるしかないと思い悩みながら、雨宿りをしようと羅生門の楼に上ると、そこに1人の老婆がいました。
老婆は、死人の髪の毛を1本ずつ抜いて、それをかつらにするのだと下人に言いました。その行いは、自分が生きるためには仕方のないことなのだと正当化します。
それを聞いた下人は、それなら自分がこうするのも仕方のないことだと思い、その老婆の着ているボロボロの着物をはぎ取り、奪って逃げ去りました。
ちょっと分かりにくいでしょうか。
この話の肝は、「下人の心の変化」です。
その部分を中心に、もう少し詳しく見ていきましょう。
詳しいあらすじ

時は平安末期。京の都は、ここ数年に起こった天変地異で荒廃しきっています。都の南の端の羅生門は、死体の捨て場となっていました。
生きている者は誰もいない。そんな寂しい場所に、1人の下人がやって来ます。
雨が降っていて、もうすぐ夜になる…。今夜の寝床をどこにしようと考え、下人は羅生門の上の楼にのぼります。
★ 悪人(盗人)になろうかと迷う心
職を失った若い男(下人)は、羅生門に上り、「このままでは餓死するので、生きていくためには盗人になるしかない、でも、そこまで堕ちてよいものだろうか」と途方に暮れていました。現代流にいうと、うじうじと悩む貧民ニートです。
悪人=盗人になりきれない下人の心の揺れを感じます。
★ 悪人を憎む正義の心
すると、だれもいないと思っていたそこには、老婆が1人いました。老婆は、若い女の死体から、髪の毛を一本また一本と抜き取っています。
それを見た下人に、あらゆる悪に対する反感がわき上がってきました。
悪は許せないと思った下人は、老婆に刀を突きつけ、ここで何をしているのかと強く問いただします。ここで、なぜか正義の味方の意識になっちゃいます。
★ 悪を憎む心がすっと冷めてくる→正義感が薄れる
下人が何をしているのか聞くと、老婆は、死人の髪をかつらにして売るのだ、生きていくためには仕方のない事だと悪びれる様子もなく言います。
ここに捨てられた死人は、みんな相応の悪事を働いたものばかりで、この死んだ女も、蛇を干した魚だと偽って売っていた悪人だったと。
しかしそれも、この女が生きるためにしたことなので、仕方のない事だと老婆は続けます。う~ん、言われてみれば、こんなご時世だしね~。政治が悪いんだよねって感じでしょうか。
★ 自分が盗人になるのは仕方のない事だ→悪になる心
老婆の言い訳を聞いているうちに、下人の心は変わっていきます。
そして、それならば、自分がこうするのも餓死しないために仕方のないことなのだと正当化し、老婆の着物を奪い取って、逃げ去ったのです。
そんな理屈を言うなら、自分が搾取されても文句はいえんだろ、婆さん!という感じですね。。
しばらくして、けりたおされた老婆が起き上がり、はしごの下をのぞくと、そこには夜の闇が広がるばかりでした。
下人の行方は、誰にもわかりません。
読書感想文のポイント

この話の元ネタとの大きな違いは、『今昔物語集』で元から盗人だった主人公が、『羅生門』ではまだ盗人になっていない下人として登場するところです。
『羅生門』の下人には、「盗人(悪)になる」or「盗人にならずに餓死してでも踏みとどまる」という2つの選択肢がありました。
でも結局、下人は、自分で盗人になる道を選びました。途中、悪を許さないという正義の心になったにもかかわらず、です。
最後には「自分が生きるため」というエゴイズムを、善悪の判断よりも優先してしまったのです。
本作品は「ある日の暮方の事である。」という一文からはじまります。
昼から夜に変わる夕暮れ時こそ、「人間の本質」が最もよくあらわれる時間帯だといいます。
闇に近づく逢魔が時。下人は、私欲を優先する心を選択したのでした。
この下人の心の揺れは、私たちみんなに覚えのあるものです。
例えば、校則違反は良くない事と分かってはいても、みんながやっているからいいやと思ってした経験や、仕方がなかったと正当化した経験などです。
そういう自分自身の体験を思い返しながら、下人の心についての感想をあらわすとよいでしょう。
下人に自発的に選択させたところ、それを読者に伝えたところに、芥川流の面白さが出ていると思います。
おわりに

明治から大正時代、日本は近代西洋の個人主義思想の影響をうけ、人間中心の考え方が文学作品にも強くあらわれます。
個人の主体性の尊重は、人間の自我・エゴイズムの問題につながります。
そのような視点で『羅生門』をよむと、夏目漱石の『行人』『こころ』などに描かれたエゴイズムを、その門下生の芥川もとらえていたのがわかります。
他人の不幸を踏み台にして、自分が利を得るという人間存在のエゴの問題に23歳でこれだけ鋭く切り込めたというのは、凄いなと思う半面、やっぱり暗いなぁと思ってしまうのでした。(´・ω・)
でも、好きな作品です。
芥川龍之介の作品は短編が多いので、1つの文庫に5作以上入っていることが多いです。ですから、出版社によって複数の本に載っている場合もあります。気をつけてくださいね。
私は文字が好きなので新潮か角川がお気に入りなのです。(表紙も大事♪)
↓
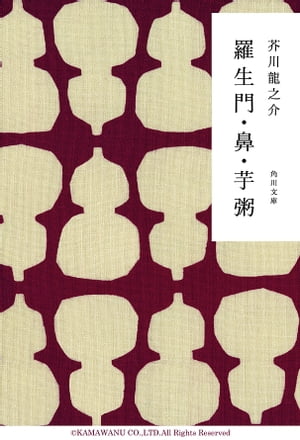 |
|
【関連記事】
↓