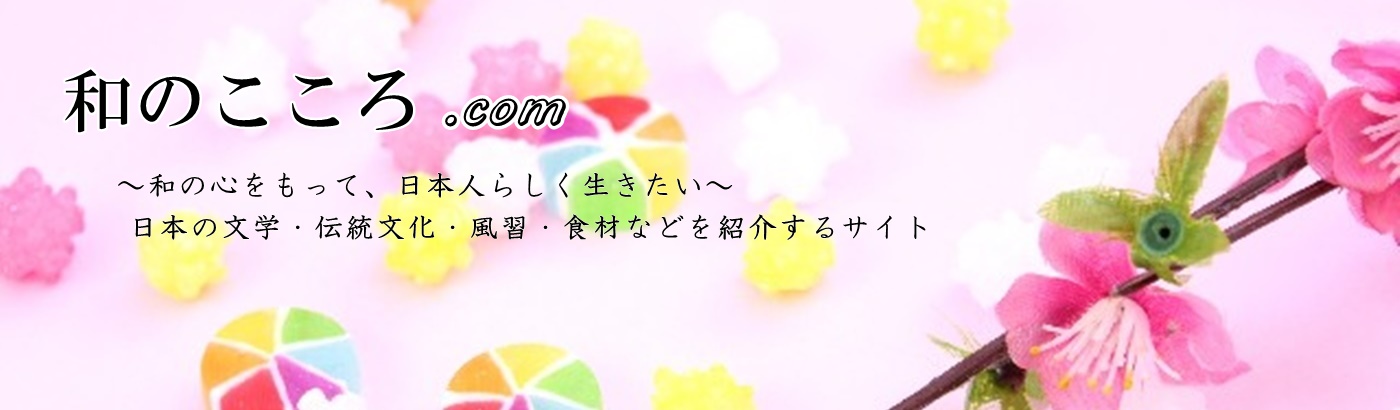この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。
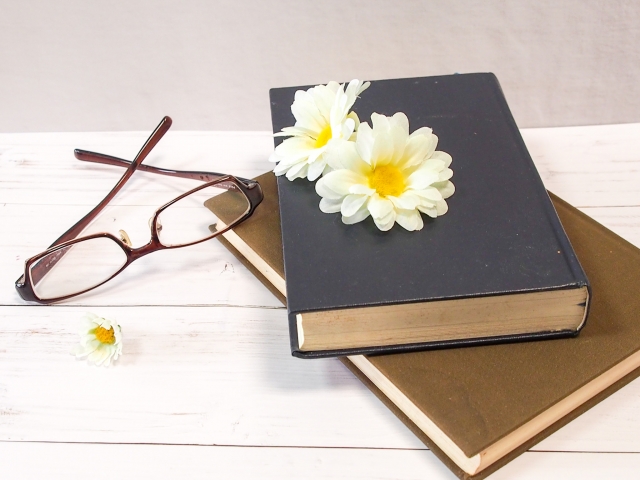
こんにちは、百華です。
近代(明治時代)から現代に活躍した日本の女性作家を紹介します。
才能にあふれ、ときには社会に反抗してペンをとり続けた女性たち。
男性による、男性目線の近現代文学とは全く違う面白さがありますよ!
~明治時代~

近代国家には、家主の男性に大きな権限を与える家父長制(かふちょうせい)のしくみがありました。
自由を求める女たちは、自分の性を主体とした作品で自己を主張します。
また、雑誌『青鞜』は彼女らが歌を詠んだり作品を発表したりする場で、のちに女性解放の思想をかかげます。
しかし、女性作家という存在は白い目で見られがちな、窮屈な時代でした。
・三宅花圃(みやけ かほ)
(1868~1943年)
近代初の女性作家
『藪の鶯(やぶのうぐいす)』(1888年)
・木村曙(きむら あけぼの)
(1872~1890年)
少女小説の第一人者
『婦女の鑑』(1889年)
・清水紫琴(しみず しきん)
(1868~1933年)
女権運動家でもあった
『こわれ指環』(1891年)
・樋口一葉
(1872~1896年)
薄命の閨秀作家 社会の底辺にも目をむける
『たけくらべ』
『にごりえ』
『十三夜』 (1895年)
・若松賤子(わかまつ しづこ)
(1864~1896年)
翻訳家 言文一致にとりくむ
『小公子』(1890年~)
・小金井喜美子(こがねい きみこ)
(1870~1956年)
森鴎外の妹 翻訳家
『皮一重』(1900年) ……清朝末期『聊斎志異(りょうさいしい)』の翻訳
・田村俊子(たむら としこ)
(1884~1945年)
女性初の職業作家 『青鞜』に参加 舞台女優もしていた
『あきらめ』 (1911年)
『生血』 (1911年)
『彼女の生活』(1915年)
・水野仙子(みずの せんこ)
(1888~1919年)
田山花袋の元弟子 結婚生活に挫折
『神楽坂の半襟』(1913年)
・与謝野晶子
(1878~1942年)
情熱的に自我を解放 恋愛賛美 浪漫主義の歌人
『みだれ髪』(1901年)
・山川登美子(やまかわ とみこ)
(1879~1909年)
与謝野晶子・鉄幹と歌を詠む
『恋衣』(1905年) ……晶子らとの共著
・大塚楠緒子(おおつか くすおこ)
(1875~1910年)
才色兼備 夏目漱石が失恋…?
「お百度詣」(1905年)
『露』(1907年)
・長谷川時雨(はせがわ しぐれ)
(1879~1941年)
女性劇作家 舞踊や歌舞伎の現代化をめざした
『海潮音(かいちょうおん)』(1905年)
~大正時代~
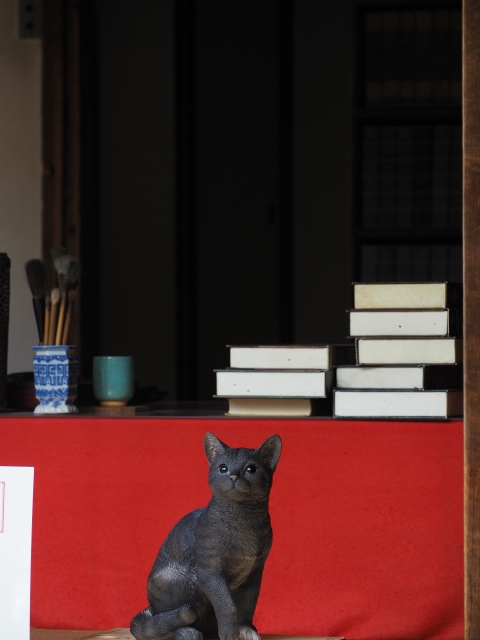
3つの戦争を経て社会の動きも大きく変わり、職業につく女性が急増した時期です。
押しつけられた結婚・出産から逃れ、個人同士の自由恋愛や社会的自立を夢見るも、待っているのはきびしい現実でした。第一次世界大戦後にさかえたプロレタリア文学に転向する作家も多くいます。
・野上弥生子(のがみ やえこ)
(1885~1985年)
夏目漱石に教わる 自由結婚に成功
『海神丸』(1922年)
『真知子』(1931年)
『秀吉と利休』(1964年)
・宇野千代(うの ちよ)
(1897~1996年)
実業家でもあった美女
『脂粉(おしろい)の顔』(1921年)
『色ざんげ』(1933年)
『おはん (1957年)
・宮本百合子
(1899~1951年)
離婚後、プロレタリア作家へ
『貧しき人々の群れ』(1916年)
『伸子』 (1924年~)
・網野菊(あみの きく)
(1900~1978年)
義母がたくさんいた 師匠は志賀直哉
『光子』(1926年)
・吉屋信子(よしや のぶこ)
(1896~1973年)
少女小説を多く執筆
『花物語』(1916年~)
『屋根裏の二処女』(1920年)
~昭和時代~
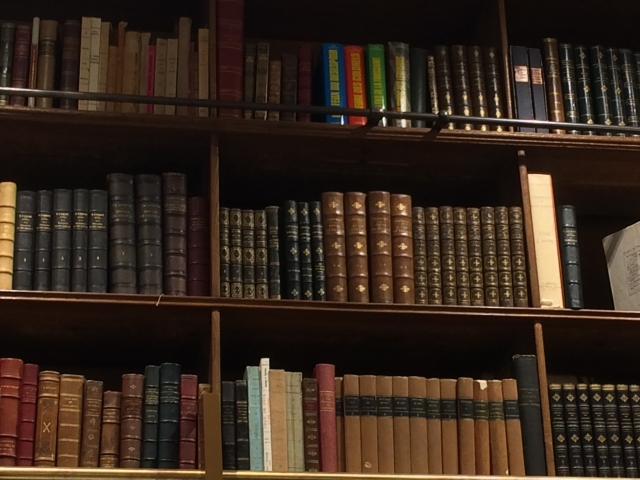
1929年の金融恐慌,1931年以降の十五年戦争で、女性も戦時体制に従わざるをえなくなりました。
プロレタリア文学運動の背景にあった、社会主義の革命思想も色濃くなっていきます。
有閑階級のお嬢様から労働者へと、作品のヒロイン像が変化したのも特徴です。
例外的な存在は岡本かの子や壺井栄ですが、それでも戦時色を抜きにして鑑賞されることは稀です。
戦後は新憲法で男女平等が掲げられ、新しい風がはいってきました。社会問題と向き合ったり、近代家族の仕組みを問い直す作品が多くうまれています。
個人の多様性は、これからも広がっていくのでしょうか。
・平林たい子
(1905~1972年)
反逆のプロレタリア作家
『施療室にて』(1927年)
・佐多稲子(さた いねこ)
(1904~1983年)
社会の動乱を見すえる
『キャラメル工場から』(1928年)
・林芙美子(はやし ふみこ)
(1903~1951年)
放浪して自己形成 詩人でもあった
『放浪記』(1928年~)
『浮雲』 (1949年)
『めし』 (1951年)
・尾崎翠(おざき みどり)
(1896~1979年)
近年、再評価がすすむ
『第七官界彷徨』(1930年)
『こほろぎ嬢』 (1932年)
・岡本かの子
(1889~1939年)
歌も詠んだ 愛人が複数(!) 息子は岡本太郎(画家)
『母子叙情』(1937年)
『老妓抄』 (1938年)
・五島美代子(ごとう みよこ)
(1897~1978年)
幸福な生活を送った歌人
『暖流』(1936年)
・大田洋子
(1903~1963年)
広島の原爆体験を報告
『屍の街』(1948年)
・壺井栄
(1899~1967年)
児童文学にもとりくむ
『二十四の瞳』(1952年)
・円地文子(えんち ふみこ)
(1905~1986年)
近代の男に物申す!
『女坂』(1949年~)
『妖』 (1957年)
・幸田文(こうだ あや)
(1904~1990年)
幸田露伴の次女 生活者の知性と感性が光る
『父―その死』(1949年)
『流れる』 (1956年)
『おとうと』(1956年)
・森茉莉(もり まり)
(1903~1987年)
森鴎外の長女 耽美的な愛の世界を描く
『父の帽子』(1957年)
『恋人たちの森』(1961年)
『甘い蜜の部屋』(1975年)
・瀬戸内寂聴(せとうち じゃくちょう)
(1922~2021年)
何かとメディアに注目されがち
『花芯』(1957年)
・中城ふみ子
(1922~1954年)
大胆に自我を主張した歌人
『乳房喪失』(1954年)
・石垣りん
(1920~2004年)
生活に根ざした詩をかく
『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』(1959年)
・河野多恵子(こうの たえこ)
(1926~2015年)
性を追求
『幼児狩り』(1961年)
『みいら採り猟奇譚』(1991年)
・倉橋由美子
(1935~2005年)
実存主義に傾倒
『パルタイ』(1960年)
・大庭みな子(おおば みなこ)
(1930~2007年)
アラスカへ飛び出す
『三匹の蟹』(1968年)
『津田梅子』(1990年)
・山崎豊子
(1924~2013年)
鋭い目で社会の暗部をみる
『暖簾』(1957年)
『白い巨塔』(1965年~)
『華麗なる一族』(1973年)
・馬場あき子
(1928年~)
高い知性と感性を生かした歌人
『鬼の研究』(1971年)
・新川和江(しんかわ かずえ)
(1929年~)
大らかな詩をかく
『わたしを束ねないで』(1996年)
・有吉佐和子
(1931~1984年)
ベストセラー作家
『紀ノ川』(1959年)
『華岡青洲の妻』(1967年)
・田辺聖子
(1928~2019年)
古典の訳も出版
『姥ざかり』(1981年)
『ジョゼと虎と魚たち』(1984年)
・津島佑子
(1947~2016年)
太宰治と津島美知子の娘
『火の河のほとりで』(1983年)
『火の山―山猿記』(1996年~)
・山田詠美
(1959年~)
漫画家でもある
『ベッドタイムアイズ』(1985年)
『カンヴァスの柩』(1987年)
・俵万智
(1962年~)
軽快な短歌で人気に
『サラダ記念日』(1987年)
~平成から現在~
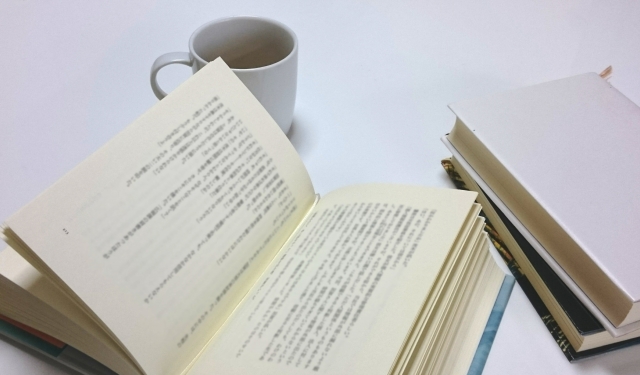
・小川洋子
(1962年~)
『妊娠カレンダー』 (1991年)
『博士の愛した数式』(2003年)
・あさのあつこ
(1954年~)
『バッテリー』(1996年~)
・川上弘美
(1958年~)
『蛇を踏む』(1996年)
『神様』(1998年)
・綿矢りさ
(1984年~)
『蹴りたい背中』(2003年)
・川上未映子
(1976年~)
『乳と卵』(2007年)
以上、近現代に活躍する日本の女性作家でした。
(参考:岩淵宏子他編『はじめて学ぶ日本女性文学史【近現代編】』ミネルヴァ書房 2005年2月15日)
【関連記事】