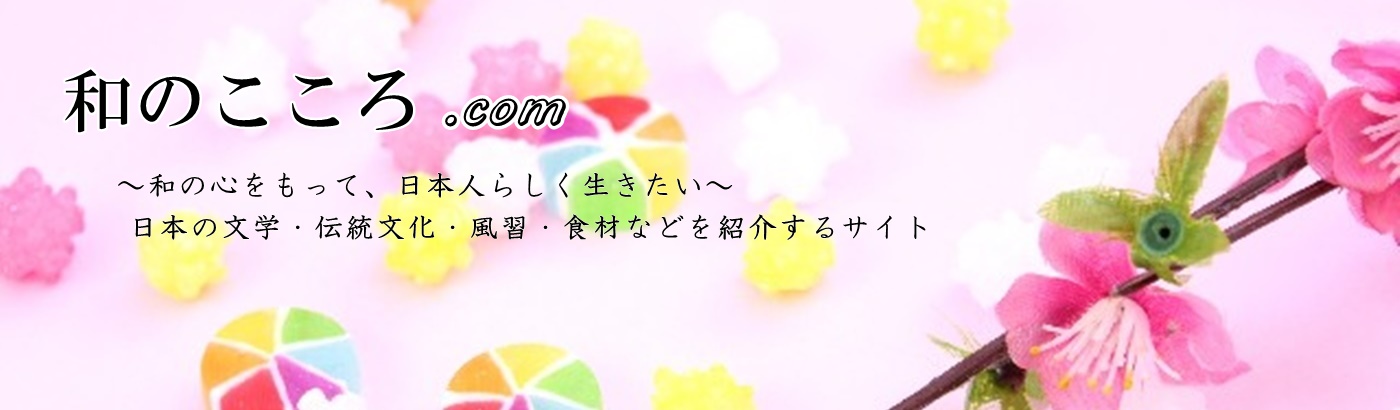この記事を読むのに必要な時間は約 17 分です。

日本の俳人といえば、松尾芭蕉、与謝蕪村、小林一茶など、江戸時代の人が有名です。江戸時代といえば、それまで貴族や武士の文化だった和歌が俳諧が、庶民の娯楽となった時代なのです。
それからかなり後、明治時代に、正岡子規が時代を代表する俳人として取り上げられます。
正岡子規は、俳句の歴史の中で、非常に重要な役割を果たしている人です。
今回は、正岡子規が俳句にとってなぜ重要な人といわれるのか、そのポイントを説明します。
目次
正岡子規の生い立ち

正岡子規は1867年に、松山藩(愛媛県)の下級藩士の長男として生まれました。
子供の頃は病弱で内気な性格だったので、いじめられっ子だったそうです。
4歳のとき、父親が亡くなり、正岡家の家督をつぎ、祖父が藩の儒者だったので、勉強を教えてもらいながら育ちました。
子規の暮らしていた松山は、俳句が盛んな土地柄でした。それで、若いころから河東碧梧桐や高浜虚子など同世代の俳人と知り合えたのです。
16歳のとき、文学だけでなく政治にも興味を持ち、自由民権運動の影響を受けて政治家になりたいと思うようになりました。上京したのもこの頃です。
そして、東京の第一高等中学校に入学し、そこで生涯の親友となる夏目漱石と知り合ったのでした。
その後、子規は東京大学を中退して、俳句や短歌を中心にした文学活動を始めます。
日清戦争の際には、従軍記者として大陸に渡りましたが、すぐに戦争が終わり帰国しました。
日本への帰りの船中で子規は激しい喀血をし、松山に戻って静養することになりました。
1897年、子規は俳句誌「ホトトギス」を創刊します。
そして、その翌年には「歌よみに与ふる書」を新聞連載しました。この連載記事は、俳句や短歌の世界に革新をもたらしました。
精力的に働きながらも肺結核の病状は悪化し、結核菌が脊髄に入って脊髄カリエスとなり、35歳の若さで亡くなりました。nbsp;
「俳句」という言葉を作った人

正岡子規が、近代俳句や短歌の祖として、取り上げられるのには、大きな理由があります。
それは、正岡子規が「俳句」と「短歌」の名付け親だからです。
つまり、子規は、「俳句」「短歌」という言葉と、その意味するものを確立した人なのです。
江戸時代、松尾芭蕉や与謝蕪村が活躍した時代には、「俳句」という言葉は存在しませんでした。今の「俳句」は、当時は「俳諧」の一番初めの句「発句」のことを指したのです。
そして、「短歌」はそれまで「和歌」とも呼ばれていました。もともと、古代の万葉の時代は、短歌と長歌と呼ばれるものがあったのです。平安時代になると長歌が廃れ、短歌のみが残り、それが次第に和歌と呼ばれるようになります。
つまり、「短歌」=「和歌」なのです。
「万葉に帰れ」というスローガンを掲げた子規は、これを和歌ではなく短歌と呼ぶのが正しいと主張しました。
ですから、現在、「5.7.5.7.7」音で作られる詩は、和歌ではなく短歌と呼ばれるのが普通です。
俳句の誕生の由来については、こちらをどうぞ♪
↓↓↓
【関連記事】俳句と川柳の違いはこれでスッキリ!鍵は季語と風刺の有無
子規は、俳句や短歌の発展に、ものすごい情熱を傾けていました。その34年という短い生涯で、残した俳句の数は2万を超えます。
「万葉に帰れ」をスローガンに!

江戸時代から続く俳諧や和歌は、明治時代になると、松尾芭蕉を神格化して、そのマネ事をする質の悪いものとなっていました。
それは、俳句が文学の1部であり、文学は芸術の1つだと考えていた子規にとって、由々しき問題でした。
そして、文学界で蔓延している、陳腐な装飾で飾った詩歌の表現を、なんとか変えたいと思って声を上げたのです。
彼が、もっとも素晴らしい手本と考えたのは、柿本人麻呂など「万葉の詩人」たちの歌でした。
私も古典の和歌集といえば、『万葉集』が大好きなので、過剰な装飾をせずに、ありのまま見た物を歌にするのがよいという子規の主張には大賛成です!
子規が、その著書『歌よみに与ふる書』の中で誉めている人に、源実朝がいます。源実朝の歌は私も大好きなので、うれしいですね。
源実朝は、鎌倉幕府第3代将軍で、源頼朝と北条政子の息子です。
鎌倉で暮らす武士なのに、都の貴族・藤原定家と仲が良く、『万葉集』を届けてもらって大喜びしたり、定家に文通で和歌を教えてもらったり、「金槐和歌集」という歌集を作ったりした文化人でもありました。
でも、都人(みやこびと)に和歌を習っても、やはり彼は武士です!鎌倉武士らしいダイナミックな動きのある歌を、たくさん残しているんですよ。
この人の和歌は、ユニークな力強さがあって、本当に素敵なんです。余談ですが、太宰治も実朝が好きで『右大臣実朝』という作品を残しています。
【関連記事】「百人一首」93番・鎌倉右大臣の和歌はこちら!
子規の、簡潔に見た物を表現することが一番、「万葉に帰れ」と強く主張したところに、すごく共感できるのでした。
松尾芭蕉を否定し与謝蕪村を高評価
正岡子規は、評論『芭蕉雑談』の中で、松尾芭蕉の有名な俳句をばんばん批判しました。
当時、松尾芭蕉は、俳人たちの間で神格化されるほど、お手本と考えられていたので、これは大きな議論を呼ぶことになります。
子規の批判の理由は、芭蕉の俳句には散文的な要素が多く、詩としての純粋性が欠けているというものでした。
その一方で、彼はそれまであまり評価されていなかった与謝蕪村の俳句を高く評価しています。
蕪村の俳句のほうが、表現が洗練されており、強い印象を与えると評価したのです。
正岡子規は、西洋美術かぶれな所があったので、写実的な西洋美術の影響も、大きく受けていたと思いますよ。
正岡子規の有名な俳句

正岡子規の俳句で、万葉好きな子規らしさが出ているなと思う5つの俳句を紹介します。
(1)柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺
「法隆寺からの帰りに、近くの茶屋で休憩して柿を食べたら、法隆寺の鐘の音が聞こえてきたなあ。」
こちらは、すごーく有名な俳句です‼
この句を詠んだとき、子規はすでに肺結核で闘病中でした。
「柿」は、正岡子規の大好物です。この俳句には前置きとして「法隆寺の茶店にて」という言葉があります。
でも、この作品は、子規がその鐘の音を聞いたのではなく、想像して詠んだのではないかといわれているところが、興味深いのです。
この俳句には、実は隠れたエピソードというか、説があります。友人の夏目漱石の俳句に、こういう作品があるのです。
「鐘つけば 銀杏ちるなり 建長寺」
この俳句、似ていると思いませんか?
実は、子規の「柿食えば…」の句は、この俳句にかけて詠まれたものといわれています。友人の夏目漱石に、感謝と友情の気持ちを表して詠んだのではないかと考えられているんですよ。
夏目漱石と子規は親友で、病床にあった正岡子規を自分の下宿先に引き取って世話をしたり、奈良への旅費など資金面の手配も、ずっとしてあげていました。
漱石がロンドン留学中、死の10か月前に、子規が
「僕ハモーダメニナツテシマツタ」
という手紙を送ったというのは、有名な話です。
漱石の留学中に子規は亡くなり、この後、2人の再開は叶いませんでした。
【関連記事】
(2)鶏頭の 十四五本も ありぬべし
「庭先に鶏頭が、14、15本ほどもあるだろうか」
この句を詠んだとき、子規はかなり病が重くて、もうほとんど歌会には参加できませんでした。結核菌が脊椎に入り、脊椎カリエスになって、歩けなくなっていたのです。
この俳句は、この時期の子規が参加した、数少ない歌会での作品なのです。
脚色を一切しない、見事な「写生」の句です。
でも、この句、そのまま読むと、
「鶏の頭が14~15本あるって、だからどうなの?」
という、すっごくつまらない句ともとれます。
実際、発表当初の評価は低かったのですが、後にこの句は、「鶏頭論争」とよばれる論争を巻き起こしました。
陳腐でつまんない句だと低評価する人と、病床の子規が庭の元気な鶏の頭が見える様子を詠むことで、「対比の世界観」を連想できると高評価する人に分かれたのです。
実際に、子規がそんな連想を狙って詠んだかどうかは謎ですが、多くの文化人に注目されたというのは確かなのでした。
(3)風呂敷を ほどけば柿の ころげけり
子規は「柿」が大好物だったので、柿を詠んだ俳句をたくさん残しています。
この作品も、「写生」ですね。
子規は、それまで最高に評価されていた松尾芭蕉の俳句を批判し、あまり認められていなかった与謝蕪村の俳句を高く評価しています。
この俳句を見ると、なんとなく蕪村の似てるなあと思いませんか?
子規は、簡潔な描写で視覚に訴える蕪村の「写生」の手法を取り入れて、多くの作品を発表したのです。
【関連記事】
(4)いくたびも 雪の深さを 尋ねけり

「子規庵」↑↑↑
「どれほど雪が降った? どれほど積もった?と、何度も尋ねてしまうものだなあ。」
この句も、よく知られています。
当時、すでに東京の「子規庵」で、子規は寝たきりの生活をしていました。
病で床から起き上がることもできなくなったため、自分の力で外の雪の深さを見に行くことができなかったんです。
ですから、何度も、何度も、周りの人に、こう尋ねていたのですね。
この俳句からは、体は不自由だけれど、雪が降ったことを子供のように喜んではしゃいでいる、子規の無邪気な気持ちがうかがえて切ないです。
(5)糸瓜(へちま)咲きて 痰のつまりし 仏かな
「薬になる糸瓜の花が咲いたけれど、痰がつまってすでに仏(死人)同然のこの身には、間に合わないだろうなあ。」
大変有名な1句です。
子規は、死の前日に、3つの俳句を書き上げ、そのまま筆を落として昏倒したという話が残っています。
それが、「正岡子規の絶筆三句」とよばれるもので、そのうちの1つがこの句です。
当時、糸瓜(へちま)の茎からとれる「へちま」水は、痰切りの薬として使われていました。肺結核だった子規は、それを薬にしようと育てていたのです。
「仏」は、仏様やブッダを意味しますが、もう1つ、亡くなった人を表す場合があります。
この句で使われているのは、この後のほうの意味ですね。
もちろん、この俳句を詠んだとき子規はまだ生きていましたが、薬にしようと思って植えた糸瓜(へちま)の花が咲いたけど、もう、自分には間に合わないなとあきらめているのです。
すでに、自分の死が近いのを、悟っていたと分かります。
切ない俳句ですが、死の間際まで、俳句を作ろうとしていたというところに、執着ともとれる子規の情熱を感じます。
【関連商品】
↓
(クリックでAmazonに飛びます)
俳句のルールをさらっとしっかり押さえたい初心者におススメの本です。
(クリックでAmazonに飛びます)
歳時記は、この本が読みやすくて量もちょうどよいです。