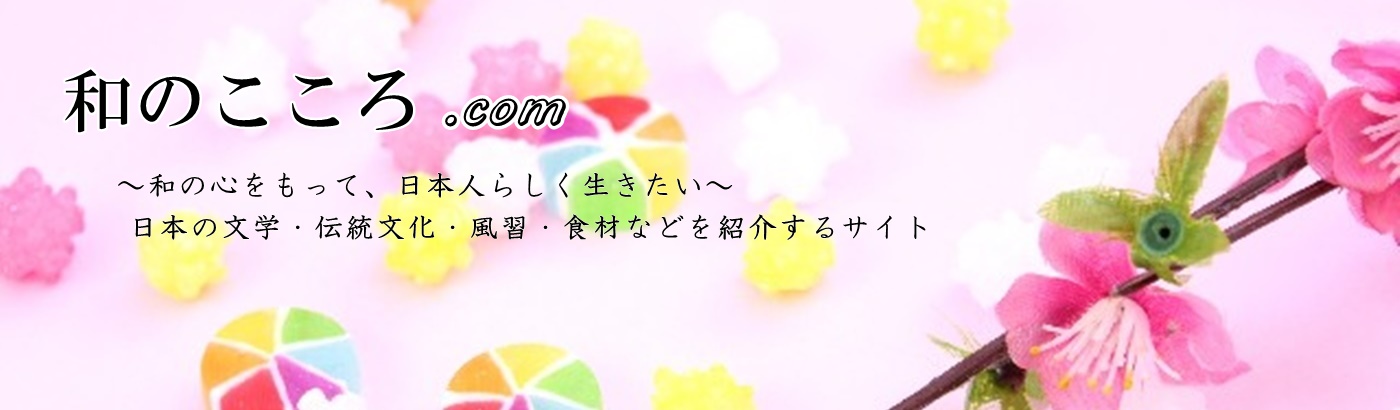この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。

「女生徒」は太宰治の中期の作品です。
太宰治は、20代で数度の自殺(心中も)未遂、パビナール中毒になり、いったん筆を折りますが、30歳で転機が訪れます。
再婚して精神的に落ち着いたこの頃に、太宰はいくつかの名作と呼ばれる作品を生み出しました。
「女生徒」は、その1つです。
太宰の大まかな年表はこちらにあります。↓
「女性徒」は、少女の一人称の視点による、体験と内面の告白でできています。
太宰治は、この女性の「一人称告白体」が得意な作家です。
「斜陽」「燈篭」「千代女」など、この文体の作品も多いです。そして、どれもこれもなぜ?と思うほど女子っぽいです。
この作品は、発表当時、川端康成に絶賛されたことでも、知られています。
「女生徒」冒頭
あさ、眼をさますときの気持ちは、面白い。かくれんぼのとき、押し入れの真暗い中に、じっと、しゃがんで隠れていて、突然、でこちゃんに、がらっと襖をあけられ、日の光がどっと来て、でこちゃんに「見つけた!」と大声で言われて、………
この文は、この倍ぐらいの長さで続きます。一文が、すごく長いです。
心身共に成熟途中の少女(14歳)の、揺れ動く心がよく表れています。
「女生徒」あらすじ
「女生徒」は、主人公の「私」が朝目覚めたときから、眠りにつくまでの一連の行動と心の動きを書いた作品です。
彼女は、14歳で母と2人暮らし、メガネっ子でロココ趣味のある女の子です。
夢見るようなロマンチックな妄想をしているかと思えば、哲学的なことを考えたり、俗っぽいことを考えたりと、一貫性がありません。そんなところが、いっそう少女らしさを引き立てます。
内容は、その日の出来事を時系列に語っているだけなので、次から次へと話題が変わり、彼女の心情もコロコロ変化します。
登校時、傘を持ってパリの街を歩く自分の姿を想像し、ふと我に返って現実とのギャップに落胆したり、
登校途中に、労働者たちから厭な言葉をかけられ、泣きそうになるのをこらえて笑ってやり過ごしたけれど、こんなくだらない事に平然となれるように、早く「強く清くなりたい」と思ったり、学校では、美術の伊藤先生に絵のモデルになってほしいと頼まれて引き受けるけれど、自分を意識している先生がばかに見えたりします。
家に帰ると、お母さんがお客さんの接客中です。
このごろの、彼女のいらいらは、思春期の女の子にありがちな母親との関係にあります。
お母さんの気持ちに、ぴったり添ったいい娘でありたいけど、へんに御機嫌とるのもいやだと思います。
お母さんとの関係を考えているかと思えば、亡くなったお父さんや家を出ているお姉さんがいればなあと寂しさを感じたり、
お母さんが、人に媚びるような人付き合いをするのが嫌だと思いながら、自分もお客さんに愛想よく振舞っていたりします。
自分自身の「理想と現実」、「自分の意志を貫くことと社会的な模範と呼ばれるもの(本音と建て前)」の狭間で、自分の態度や考えがまとまりきっていないのです。
しかし、漠然と未来に希望を抱いていることも分かります。
↓ ↓ ↓
「明日もまた、同じ日が来るのだろう。幸福は一生、来ないのだ。それは、わかっている。けれども、きっと来る、あすは来る、と信じて寝るのがいいのでしょう。」
末文は、こちらです。(‘Д’)
↓ ↓ ↓
「おやすみなさい。私は、王子さまのいないシンデレラ姫。あたし、東京の、どこにいるか、ごぞんじですか? もう、ふたたびお目にかかりません。」
おわりに

この話は、ストーリーや構成を追うのではなく、純粋に独特の表現を楽しむ作品です。「人間失格」とは、全然違う軽やかさです。
私は、太宰治の文章よさは、こういう作品にあると思っています。短編小説のほうがおもしろいです。
この話の題材は、太宰治の元に送られた女性からの「ファンレター」です。
ファンレターの内容にどこまで忠実なのか不明ですが、一通に手紙からこれほど内容を膨らませて書けるところに技量を感じます。
そもそも30歳男性の太宰治が、どうしてこれほど少女の内面描写を一人称で語れるのか、そのあたりからして不思議です。
なによりすごいのは、思春期の女の子のコロコロ興味の対象が移り変わる心理を、これだけ表現できているところです。
もしかして、男性だからこそ書けたのか? などなどいろいろ考えされられます。
【関連記事】