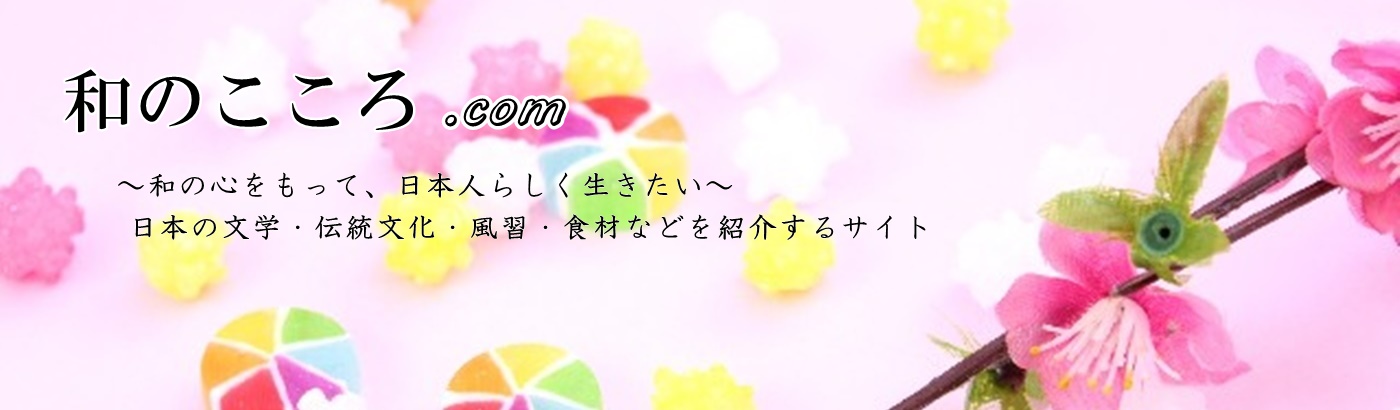この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です。

紫式部の大長編作品『源氏物語』は、恋だけでなく立身出世、宮中の陰謀策略など多くのテーマが描かれています。
でも、始めから最後までシリアスな話ばかりだと、疲れてしまいますよね。
紫式部はそういうところもしっかり分かっていて、ちょっとゆるい笑える話をところどころはさんで息抜きさせてくれています。
たとえば減典侍(げんのないしのすけ)という年配の女性とのいきさつや、とんでもない不器量な姫・末摘花(すえつむはな)の話などです。
特に末摘花は、うわべのあらすじだけを追うと、そのヘンな顔をいじっただけの笑い話かと思えますが、実は違うのです!
末摘花は、素晴らしく高貴な精神を持つ女性としても描かれているのでした。
今回は、数多く美女が登場する『源氏物語』の中でひときわ目立つ不器量で気の利かない姫、末摘花についてお伝えします。
目次
不美人で内気な女性「末摘花」

末摘花は『源氏物語』の中で6つの巻に登場し、『末摘花』と『蓬生』の2つの巻では、メインの人物として描かれています。
『末摘花』の巻は、光源氏がラブハントを繰り返していた若い頃の話です。
光源氏が新しい恋人を求めて、どこかに素晴らしい姫君はいないかとアンテナをはっていたところ、故常陸宮の姫君で、琴の名手の深窓の姫君がいるとのうわさを耳にしました。
ちょうどライバルの頭中将(とうのちゅうじょう)も気になっていた姫なので、先手必勝とばかりに光源氏はすぐにその姫に文を書いたのですが、返事はありませんでした。しびれをきらした光源氏は、とうとう返事を待たずに寂びれた屋敷に住まう姫のもとへ通ったのです。
相変わらず、まめな男です。
しかし、実際に会ってみると、彼は末摘花に妙な違和感を覚えました。
そして、2度目に彼女のもとを訪れたとき、光源氏は月明かりの下ではっきり彼女の顔を見ます。いえ、見てしまいました。そして、そのあまりの不細工さにびっくり仰天してしまったのでした。(失礼)
そして、彼は見なければよかったとか、わけのわからない後悔までしています。超絶イケメンが不細工な女性をいじって笑いものにしている内容なので、笑えるというより気の毒になります。
(1)末摘花の容貌と身なり

光源氏がびっくり仰天した末摘花の容姿は、こんな感じでした。
がりがりに痩せていて座高がやけに高い、そして、顔色が青白くておでこが広く顔が長い馬面でした。そして、なにより目立ったのがゾウのように長い鉤鼻で、しかもその先端が真っ赤でした。
この長くて赤い鼻というのが、末摘花の大きな特徴です。光源氏は、「普賢菩薩の乗り物のようだ」とユーモアたっぷりに表現していますが、全く笑えません。光り輝く貴公子が言ってると思うとムカつきます。
でも、彼女には、とても素敵なチャームポイントがありました。それは、豊かで長い美しい黒髪です。
それは平安女子にとって、とても大切な「美の条件」でした。
末摘花の装いはとても古風だったのですが、これまた古風というのを通り越して、光源氏は古臭くてダサいとしか思えませんでした。
すっかり古くなって色も変わっている着物の上に、なんと、香をたきしめた黒てんの皮衣の上着を着ていたのです。
平安女子の着物の上に、黒い毛皮のチョッキです。これは、現代の感覚でも、かなりやぼったく感じます。
毛皮は当時も高級品でしたが、貴族の男性が着るものでした。でも、この頃にはすでに流行おくれのファッションだったようです。おそらく、父親の常陸宮が着ていたものなのでしょう。
(2)愚鈍で気の利かない女性かも?

末摘花は、故常陸宮の姫君です。
つまり最上流の宮家の姫君だったのです。しかし、常陸宮家は凋落し、今では、身の回りに気の利いた女房もおらず、生活にも事欠くありさまでした。
着物が野暮ったいのは、新しい着物を用意できないからでもあったのです。また、周りに優秀な教師となる女房がいなかったので、「文」もよれよれの古びた和紙に下手くそな字で書いていました。
もう、豊かな黒髪以外は、いいとこなしです。
彼女は融通が利かなくて、自分が父から教わった教養の範囲内でしか物事を判断することができません。そして、それを正しいと信じてけっして曲げない頑固なところがあり、読者の笑い者になるのです。
ところが、ここで笑い者にされた末摘花の時代遅れの感性や考え方は、『蓬生』の巻で全く逆の視点で描かれているのです。
そこが、紫式部のすごいところなのでした。
宮家のプライドを持つ高貴な姫・末摘花

『蓬生』の巻では、『末摘花』の巻で描かれていた末摘花の時代遅れで世間知らずなところが、今度は逆に彼女の「美質」として描かれます。
彼女の笑いのネタになっていた容姿についての描写は、ここでは少なくなっていきます。
そして、貧困に陥ってもけっして宮家の姫のプライドを捨てない意志の強さが、はっきり浮き上がってくるのです。
平安時代は女性が自分の意志で生き方を決めるのが、すごく難しい時代でした。紫式部も清少納言も、そのことで悩んでいます。でも、末摘花はけっして自分の生き方を曲げません。
彼女は、もう笑い者ではありません。
紫式部は、末摘花をとおして「心の美」の大切さを訴えたのだと思います。
「心の美しさ」は人を感動させる力を持つ

光源氏は、その後、末摘花を経済的に援助はしていましたが、朧月夜との一件で失脚して須磨に下り、すっかり彼女のことを忘れていました。
それから、また復帰して京の都に戻ってからも、全く思い出しません。
その間、彼女は困窮し、仕えていた女官も離れていってしまいました。
そんな状況のとき、受領の妻になった叔母が末摘花のもとにやって来ました。叔母は末摘花を娘の世話役に使おうとし、一緒に来るように説得します。
でも、末摘花は頑として首を縦に振りません。
どんなに貧しくても、父から譲られた高級な唐物の調度はけっして売らず、光源氏がいつか訪ねてくれると信じて待ち続けているのです。
「もうあんたなんて、とっくに忘れ去られているわよ!」とののしられても、ずっと待ち続ける彼女の一途さは、後に光源氏を感動させます。
その後、光源氏は愛人の1人の花散里を訪ねる途中、偶然そこを通りかかり、なんだか見覚えのある屋敷だなーと思って末摘花を思い出したのでした。
長い間、ずっと彼女がすっかり忘れていた自分を信じて待ち続けていたと知り、また、宮家の姫としての誇りを失わず、どんな境遇になってもおっとり上品に構えている様子に、光源氏は真の高貴さを感じて感動したのでした。
それから後、光源氏は最後まで末摘花を経済的に援助し続けました。
末摘花は意外に当時の読者に好かれていた?

末摘花は、この後も、ちょこちょこ脇役として登場します。こういうユニークな人が再登場すると、読者としてはうれしくなります。
脇役なので、和歌が下手だとか、センスがなさすぎて失礼な贈り物をしたとか、相変わらず世間知らずな道化役として登場します。
しかし、もう誰も彼女がただのダサくて不細工なだけの姫だとは思わないでしょう。
そして、彼女のような「心の美しさ」を持つ女性に感じ入り見捨てないところが、光源氏のいい男なところなんでしょう。やっぱり。
結局のところ、うっとおしい色恋沼にどっぷりはまらない、末摘花や花散里のような人のほうが、心穏やかに幸せに暮らせていたのではないかと思うのです。
【関連記事】
↓