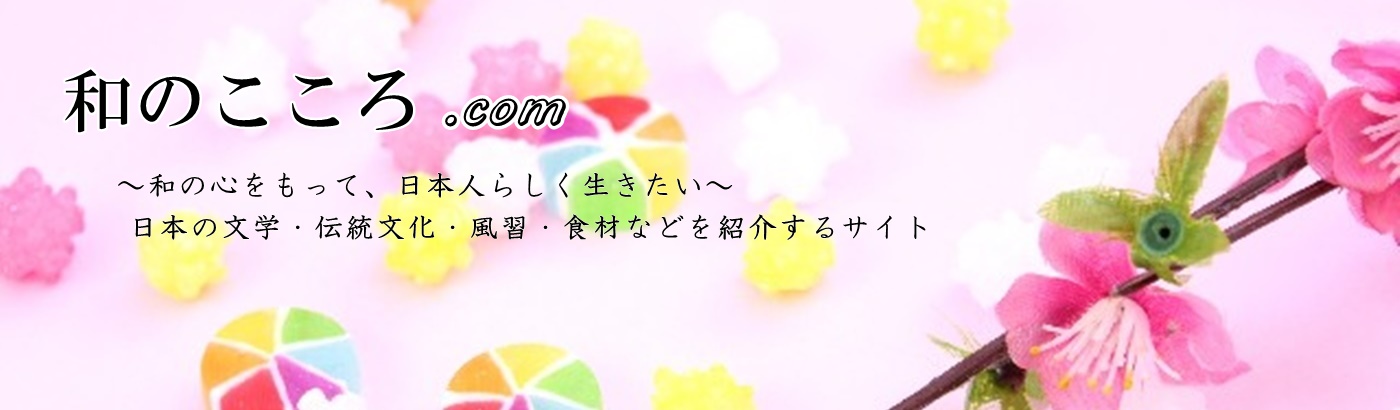この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

今回は、西行法師の第二弾をお届けします。
23歳で、約束されたエリートコースを捨て去って、流浪の歌人となった西行の生い立ちやエピソードは、こちらの記事でお伝えしています。
ご一緒にどうぞ♪(*’▽’)↓
 「西行法師」の生き様が超絶クールなわけ!花と月と放浪の歌人
「西行法師」の生き様が超絶クールなわけ!花と月と放浪の歌人
西行は、平安末期、鎌倉時代の幕開けという激動の時代に生きた歌人です。
奥州藤原氏の藤原秀衡と親類で、源頼朝にも会っています。
藤原定家の父・俊成と同世代で、定家にもリスペクトされ、後鳥羽院も崇徳天皇などとも、和歌をとおしてかなり仲が良かった人です。そして、平清盛とは武人時代(北面の武士)の同僚でした。
今回は、そんな西行が旅の途中に詠んだ和歌を中心に、お伝えします。
私の好きな西行の名歌

西行は、花(桜)と月をこよなく愛した歌人でした。
その作風は、自然や心情をありのまま歌に詠む、印象の強い歌が多いです。そして、なぜだかネガティブな心情描写が多くて素敵です。
西行の和歌を集めたものが『山家集』(さんかしゅう)と呼ばれる歌集です。
この歌集には、西行が旅の中で詠んだ1500首ほどの和歌が収められています。そして、和歌は、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」「雑」の6種類に、分かりやすくグループ分けされています。
(1)「旅・恋・人生の寂しさ」を詠んだ歌

当時の和歌は藤原定家の時代なので、「幽玄の美」を追い求めるものが主流でした。
雅(みやび)な言葉でたくさん装飾した表現が好んで詠まれたのです。
そんな中、心情を素直に吐き出し、ダイナミックな自然の美をそのまま素朴に言葉にする西行の和歌は、異端ともいえるものでした。
山の奥でひとりぼっちの寂しさを詠んだ歌が多いですが、その寂しさをじっくり味わっているような和歌がたくさんあります。
ここでは、そういう和歌を集めてみました。

● いつの間に 長き眠りの夢さめて 驚くことの あらんとすらむ
いつになれば長い迷いから覚めて、何事にも動じない心を持つことができるのだろう。
● 世の中を捨てて 捨てえぬ心地して 都はなれぬ 我が身なりけり
世の中を捨てたはずなのに、都の思い出が煩悩となって私から離れないなあ。
● 常よりも 心細くぞ 思ほゆる 旅の空にて 年の暮れぬる
いつもの年より心細く感じるなぁ。旅の空の下で年が暮れていくよ。
● 心をば 深き紅葉の色に そめて別れ ゆくや散るに なるらむ
私の心を深紅の紅葉の色に染めて別れよう。散るとはそういうことなのだなあ。
● すぎてゆく 羽風なつかし 鶯よ なづさひけりな 梅の立枝に
飛び過ぎてゆく羽風が香っていいなぁ。うぐいすよ、馴れ睦んでいたのだな、梅の咲く立ち枝 に。
● 山里は 秋のすゑにぞ 思ひしる 悲しかりけり 木がらしの風
山里は秋の末にこそ思い知るものだ、木枯らしの風が悲しいものだなあと。
● 水の音は びしき庵の 友なれや 峰の嵐の 絶え間絶え間に
峰から吹き付ける強風の中に、時々聞こえる川の音は寂しい庵の友なのだ。
● 身を捨つる 人はまことに 捨つるかは 捨てぬ人こそ 捨つるなりけれ
出家する人は本当に身を捨てているのだろうか。いや、むしろ捨てていない俗世の人こそ捨ててしまっているのだよ。
(2)「月」を詠んだ西行の和歌

★なげけとて 月やはものを 思はする かこち顔なる わが涙かな
嘆きなさいと、月が私に物思いをさせるのだろうか。いや、そんなことはない。
それなのに、すべて月のせいだといわんばかりに、こぼれ落ちてゆく涙だよ。
※この歌は、「百人一首」86番に収められています。
● ゆくへなく 月に心の すみすみて 果てはいかに かならんとすらん
どこまでも月に心が澄んでいき、この果てに私の心はどうなってしまうのだろう。
● 弓はりの 月にはづれて 見しかげの やさしかりしは いつか忘れむ
弓形の月の月光から外れて見たあの人の姿の優美さを、いつか忘れることがあるだろうか、いやないだろう。
● うちつけに また来む秋の 今宵まで 月ゆゑ惜しく なる命かな
再びめぐり来る中秋の名月の今宵まではと、ふと月ゆえに惜しくなるわが命であるなあ。
● なにごとも 変はりのみゆく 世の中に おなじかげにて すめる月かな
何事もすべてが変わってゆくこの世の中で、昔から変わらず同じ光で澄みわたるのは月の輝きだなあ。
● 都にて 月をあはれと 思ひしは 数よりほかの すさびなりけり
都にいた折に月を「あはれ」と思ったのは、物の数ではない暇つぶしのようなものであったなあ。
● もろともに 眺め眺めて 秋の月 ひとりにならむ ことぞ悲しき
一緒に秋ごとに月を眺め悟りに達しようと願ってきたのに、(上人がなくなってしまい)一人で仰がねばならぬようになるとは悲しいものだなあ。
● 荒れ渡る 草の庵に 洩る月を 袖にうつして ながめつるかな
荒れ果てたこの草庵に差し込む月光を、袖に映して眺めているよ。
● ひとり住む 庵に月の さしこずは なにか山辺の 友にならまし
独り寂しく住む庵に差す月の光は、まるで山里の友のようだ。
● 面影の 忘らるまじき 別れかな 名残を人の 月にとどめて
いつまでも面影の忘れられそうにない別れであるなあ。別れた後も、あの人の名残を月の光の中にとどめているよ。
● いかでわれ 今宵の月を 身にそえて 死出の山路の 人を照らさん
何とかして自分は今宵の月を身にそえて、死出の山路を越えていく人を照らしたいものだ。
(3)「花」を詠んだ西行の和歌

桜は、日本人の心情に訴える特別な花ですね。1300年以上も前から、日本人にとて特別な花だったのです。
そんな桜を、西行法師も心から愛しました。
『山家集』に収められている「春」の歌は170首ありますが、なんとその中の103首が「桜」の歌です。
西行は、桜の歌枕でもある吉野に、3年間、庵を結んで暮らしています。吉野には、10万本の桜の木があるそうです。ですから、春になると、山全体が見事なソメイヨシノでおおわれる桜の里なのです。
それでは、桜を詠んだ歌をご紹介します。

● 花見れば そのいはれとは なけれども 心のうちぞ 苦しかりける
桜の花を見ると、訳もなく胸の奥が苦しくなるものだ。
● 春ごとの 花に心を なぐさめて 六十(むそぢ)あまり の年を経にける
思えば60年余り、春ごとに桜に心を慰められてきたんだなぁ。
● 花に染む 心のいかで 残りけん 捨て果ててき と思ふわが身に
この世への執着を全て捨てたはずなのに、なぜにこんなにも桜の花に心奪われるのだろう。
● なにとなく 春になりぬと 聞く日より 心にかかる み吉野の山
春になったと聞いた日から、なんとなく、吉野山が気になってしかたがない。
● 世の中を 思へばなべて 散る花の 我が身をさても いづちかもせむ
世の中のことを思えば、すべてが散る花のようだなあ。さて、わが身をどうしたものだろう。
● 散る花は また来ん春も 咲きぬべし 別れはいつか 巡りあふべき
散る桜の花はまた来年咲くだろう、でも、死別した人(母)には再び会うことはできないだろう。
● おしなべて 花のさかりに なりにけり 山の端ごとに かかる白雲
いちように花の盛りになったなあ。山の端ごとに白雲がかっているよ。
● もろともに 我をも具して 散りね花 うき世をいとふ 心ある身ぞ
私を一緒に連れて散ってほしい、 桜の花よ。私もこのつらい世をいとう気持ちのある身なのだよ。
● 吉野山 桜が枝に 雪ちりて 花おそげなる 年にもあるかな
吉野山では桜の枝に雪が舞い散っている、今年は花が遅れそうな年になるだろうなあ。
● 吉野山 花の散りにし 木の下に とめし心は われを待つらむ
吉野山の散った桜の下に私の心は奪われたままだ。あの桜は今年も私を待っているのだろう。
※西行は亡くなる10数年ほど前に、遺言ともいえる有名な歌を詠んでいます。
それがこの和歌です。↓
★「願はくは 花のもとにて 春死なむ その如月の 望月の頃」
願える事なら、満開の桜の下で春に逝きたいものだなあ。2月15日頃に。
「如月の望月」というのは、お釈迦様の命日2月15日のことです。
そして、西行が西方浄土へ旅立ったのは、1190年2月16日、河内の国の弘川寺にてでした。
おわりに

西行法師を偲んだ歌碑は、日本全国に146基も建てられています。それだけ昔からファンが多いということですね。
約500年後に活躍する俳人の松尾芭蕉は、西行の作品や生き方を敬慕して、旅に生きた俳人でした。他にも、後世の多くの歌人や俳人、茶人たちに、西行の作品や人生は大きな影響を与えています。
吉野は、山深すぎて私はなかなか行く気にはなれないのですが、晩年、彼が過ごした京の西に位置する嵯峨野も、わびさびを感じられる素敵なところですよ。
こちらは、季節を問わず訪ねやすいので、おススメです。(´・ω・)
【関連記事】
↓